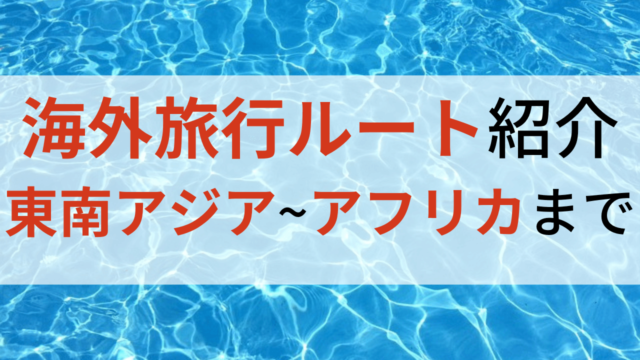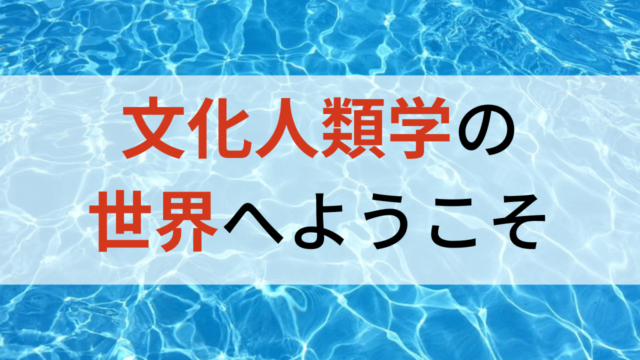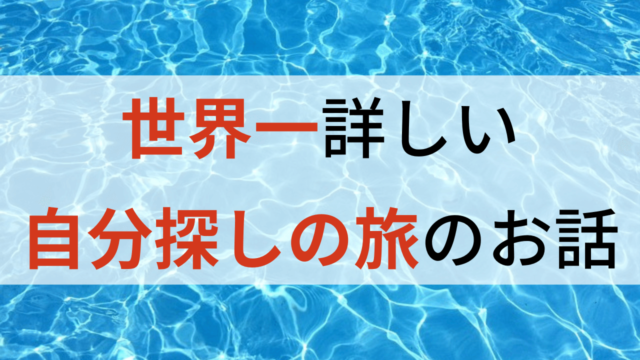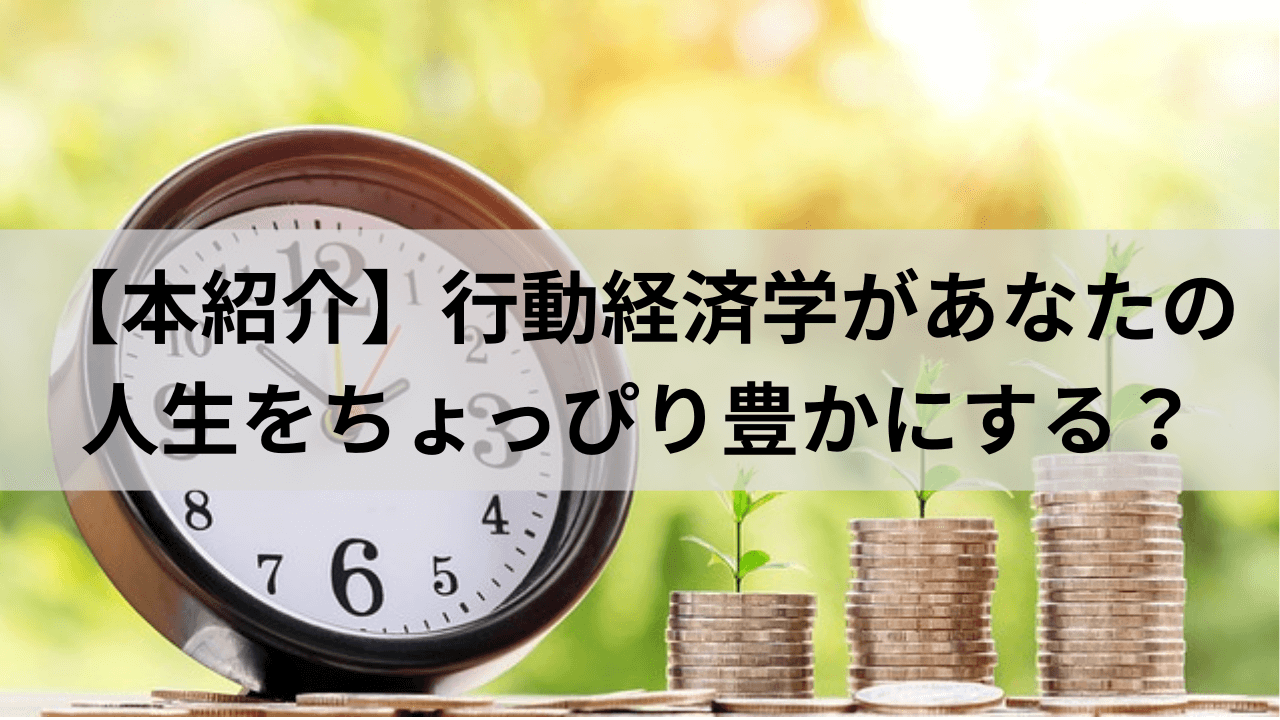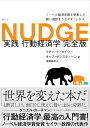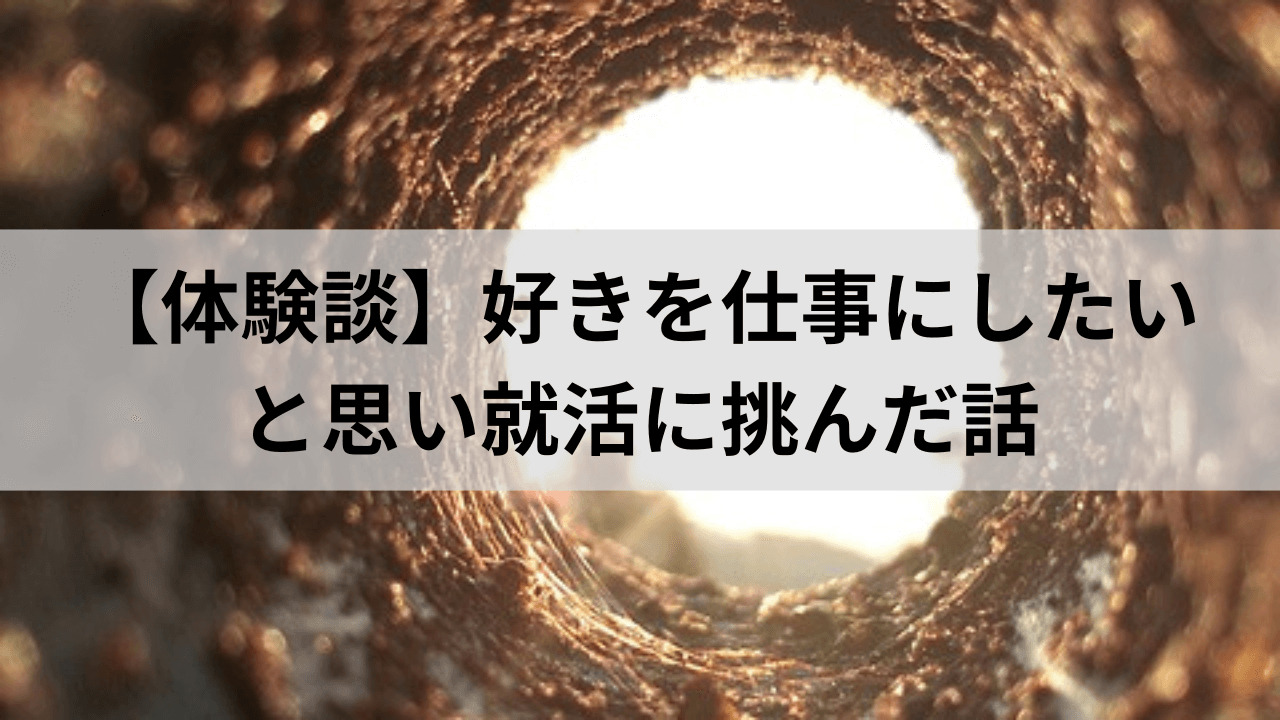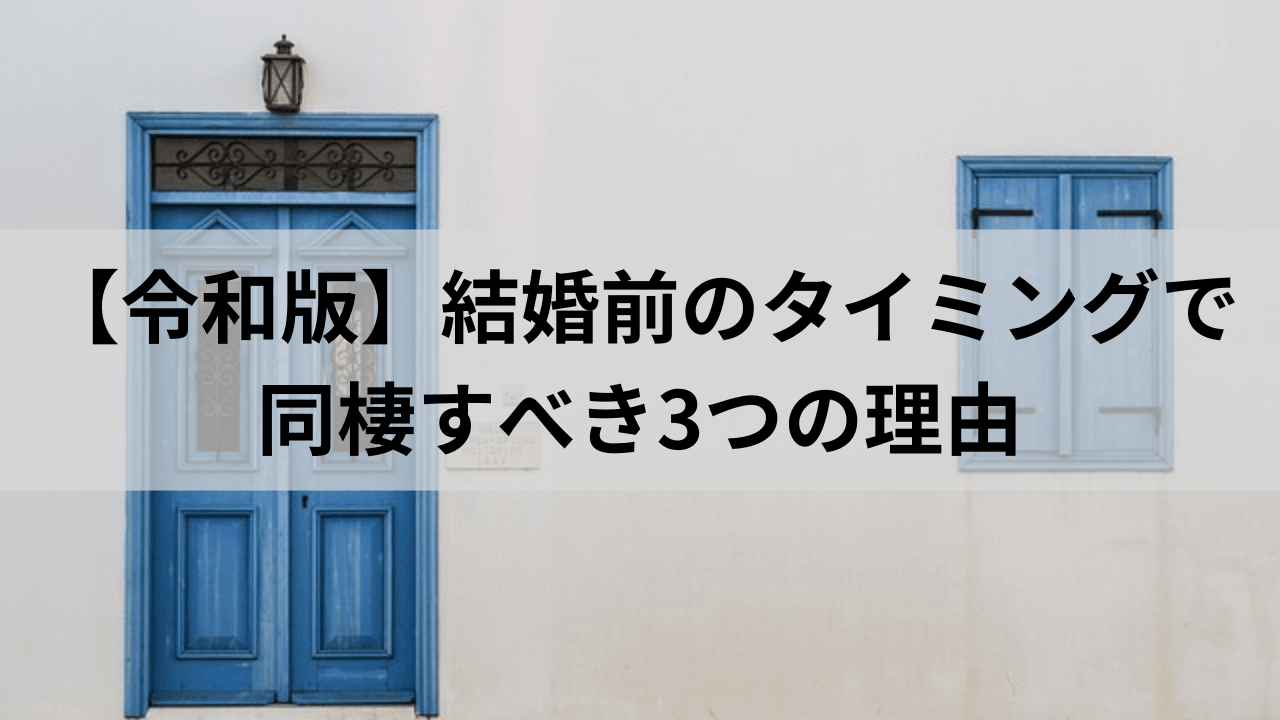行動経済学をマーケティングや仕事で活かしたい!その具体例を知りたい!
と思って調べて検索してもなかなか具体的なイメージが浮かばないこと多いですよね…
そこで今回は、私が大学時代に小さなスーパーでレジをしていた実体験をもとに、行動経済学の具体的なイメージがわくような身近な例を以下の流れで紹介していきます。
- 行動経済学の本に興味を持った背景
- 行動経済学って?
- 【実体験】行動経済学が役に立った話
- 行動経済学面白そう!って思ったアナタに
行動経済学の本に興味を持った背景

大学時代は文化人類学を研究していたのですが、その理由を簡潔に説明すると
人生が豊かになる
からなんですね。
なぜかというと、世界中の人々の生き方を知ることで多様な豊かな人生の考え方を知ることができ、
それらの知恵を基に自分の歩む道を決めることができるからです。
言い換えると、私自身常に豊かな人生を文化の観点から考えていたのですが、
ある些細な出来事から行動経済学がもっと人生を豊かに生きるヒントを教えてくれるのでは?
と思うようになりました。
その些細な出来事は会社の新人研修の時でした。
詳しいことは言えませんが、人々の思考パターンについてのお話があった際、
「これの基の理論ってなんですか?」
と何気なく講師の方に質問しました。
講師の方の丁寧な説明を聞いているとますます興味深くなりもっと詳しく知りたいと思いました。
その方にからは、「まずは基となった理論の本を読むことが大事だと」言われました。
そこで出会った本が”Thinking, Fast and Slow”でした
(実はノルウェーに留学していた際、大学院生の方に紹介してもらったことがあったのですが、当時はあまり興味がわきませんでした。悲しい…)
その本を読んでいるうちに、人々の思考特性や行動特性がどんどん明らかになり(代表的なのではSystem1やSystem2の概念ですかね)
それが自分の言動を客観的に説明しているようでした。
これはビックリ。なんせ自分の言動の大半がこの本で説明できちゃったからです。
「人生を豊かにするためには、まず自分自身のことを知らなくちゃ」と考えている私にとってこの本は神でした。
自己理解に役立つからです。
「もっと詳しく知りたい!」と思った私はその著者の経歴や出版物を調べることにしました。
そこで、行動経済学に出会ったのです。
行動経済学って?
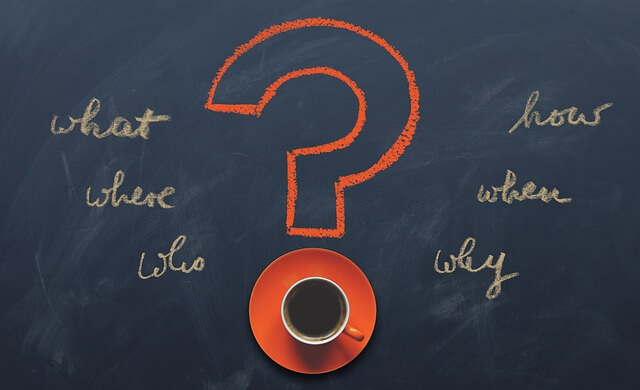
人間って全然合理的じゃないけど、その不合理な状態の中にも合理的な部分ってあるよね?
と考える学問だと勝手に解釈しています。
行動経済学の本を読んでいると、行動経済学は伝統的な経済学の「合理性」に疑問を持っていることがわかります。
私達は物事を合理的に判断することができ、日頃から合理的に生きているのを経済学は前提にしているらしいです。
そこに「んなわけね~じゃん!!」ってツッコミを入れたのが行動経済学です。
行動経済学は主に心理学の観点から人々がいかに合理的でないかを説明している印象を受けます。
言いかえると、人々は不合理なんですね。でも
その不合理な中にも共通している部分ってあるんじゃね?
とツッコミ返しをしているところが行動経済学の本当に面白いところだと感じています。
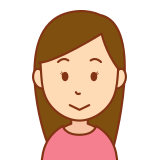
いや…全然イメージできない…
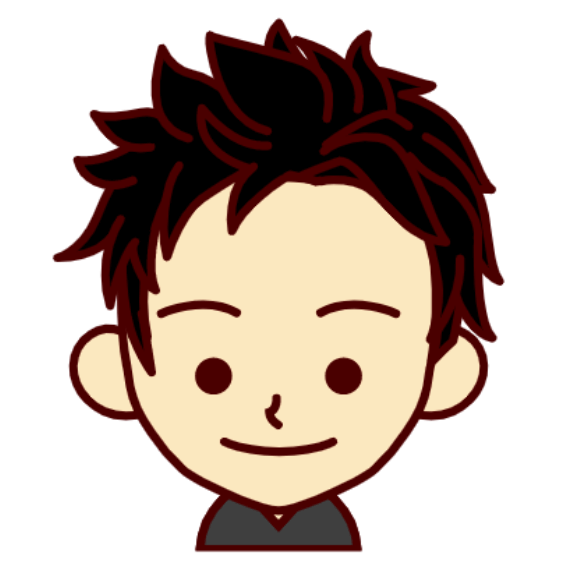
そこで、実際行動経済学の導入の本を10冊以上読んだ経験を基に、頑張って説明していこうと思います♪
【実体験】行動経済学が役に立った話

大学時代に小さなスーパーでレジをしていた際に、行動経済学が役に立った話を紹介します!
当時、プラスティックを減らす取り組みが世間で活発になってきました。
バイト先のスーパーも取り組みの一環としてレジ袋削減に取り組みました。
どうやったらレジ袋を減らせるんだろう?
レジでお客様の対応をしながら私は悩んでいました。そんな時です。
ふと、「これ絶対レジ袋いらないでしょ!!」とツッコミどころがあるシーンがいくつか見られました。
じゃあ、なぜレジ袋がいらない状況なのに、一定数の方はレジ袋をもらうのだろう?
…その理由について考えているとある仮説が思い浮かびました。
私:「袋入りますか?」
お客様:「はい」
↑この返事は本当にレジ袋が欲しい「はい」ではなく、何となく言っている「はい」ではないのか?
そう思った私はある実験をしてみることにしました。
そう、言葉をちょこっと変えてみたのです。
私:「袋なしでいいですか?」
お客様:「はい」
何とビックリ!!言葉をちょこっと変えただけで、レジ袋を削減することができたのです。でもなぜ??
そんな疑問が行動経済学の本であるThinking, Fast and Slowを読んでいるとわかる気がしました。

まず、前提として人々は2つの思考特性があります。System1とSystem2です。
それぞれの特徴を簡単に説明すると
- System1…物事を無意識・直感的に決定する「速い思考」
- System2…物事を時間をかけ、考えた上で決定する「遅い思考」
次に、「袋いりますか?」と質問した際の「はい」という返事はSystem1の思考で決定したのか、System2の思考で決定したのか考えてみることにします。
仮に当時System2の思考をお客様がしていた場合、「はい」という背景には以下の考察が可能と思われます。
「今私はジュースとお菓子とお弁当を買おうとしている。しかし、これを素手で持って帰るのは厳しい。じゃあ、袋をもらおっかな」
確かに合理的です。しかし、実際はそんなこと考えるのも面倒くさいから、
「とりあえず袋もらっとこ~」→”はい”って言っておこう
とSystem1の思考で「はい」と言った可能性が高いです。
つまり、「はい」には特別な意味がないのです。
今回はそこ(System1の思考)を逆手にとった巧妙な策でした。
「袋なしでいいですか?」・・・お客様のSystem1に訴えかけたことがレジ袋削減に繋がったのです。
確かに、「はい…いや、やっぱり袋いります!」と言うお客様も少数見られました。
これは、お客様の思考がSystem1→System2に移行したことが背景だと思われます。
つまり、
「袋いりませんか?」「はい…(あれ袋いらないって言っちゃったけど、よくよく考えたら必要だよな。だって○○だし)」…「やっぱ袋いります!」と思考が変化したわけですね。
これは本当に袋が必要な人に袋を渡せるので、袋のメリットを保ちつつ、プラスティック削減に貢献できるという一石二鳥のアイデアでした。
行動経済学面白そう!って思ったアナタに
行動経済学の本を沢山読んだそ中でもオススメは
Dan Ariely氏の「予想通りに不合理」や「ずる-嘘とごまかしの行動経済学」
ですね!単純に読みやすい!ポイントは
- 数式とかお堅いのがなく読みやすい
- 章ごとにトピックが違うので興味のあるところだけ読める(しかも各章20ページ程度!)
- 自分の経験談と照らし合わせることができるので共感でき読みやすい
この本を読んでもっと行動経済学にどっぷりつかりたい場合、Thinking, Fast and Slowがおすすめです(もちろん日本語版あります♪)。行動経済学の主要な理論を体系的に勉強できるからです。
後、投資や貯金などの$系、公共政策系だとナッジ理論等がおすすめです!
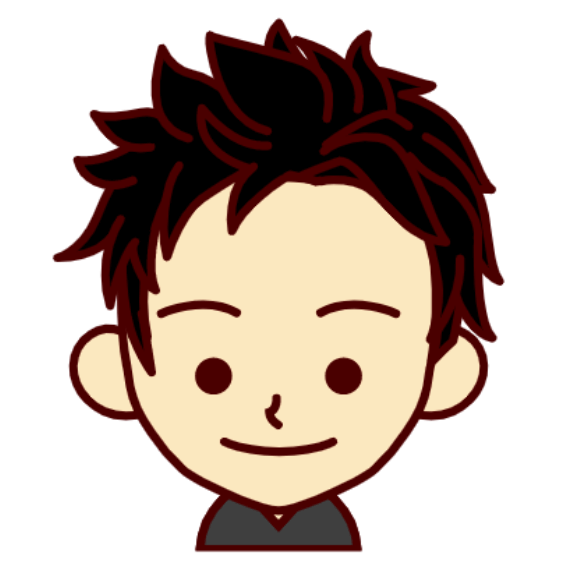
皆様のお役に立てれば幸いです!